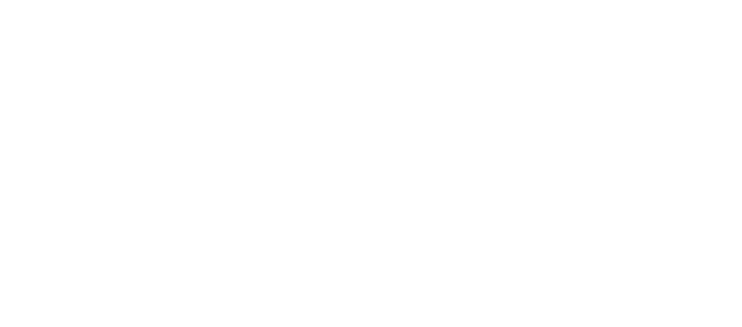焼香について

焼香とは、香をたき、香煙を仏さまにお供えする仏教の礼拝作法の一つです。香の香りをもって、仏さまを敬い、亡き方への感謝の気持ちを表します。
浄土真宗では、「香をたくことによって心を清め、仏さまを敬う気持ちをあらわす」という意味があります。焼香の回数や方法に厳格な決まりはありませんが、1回または2回香をつまんで香炉にくべ、合掌・礼拝をもってお勤めします。
焼香は、亡き方に手向けるというよりも、仏さまに礼拝し、仏法に出遇わせていただく私自身の姿勢を表すものです。静かに合掌し、阿弥陀さまのお慈悲に思いを寄せるひとときを大切にいたしましょう。
法名について

法名とは、浄土真宗の門徒として、阿弥陀如来の教えに帰依した証として授けられる仏教徒としての名前です。亡くなった後につける名前と思われがちですが、本来は、生前に仏弟子となる意味でいただく尊い名前です。
法名には、通常「釋(しゃく)」という字が付きます。これは、お釈迦さまの弟子であることをあらわしています。たとえば「釋○○」というように名づけられます。
法名は戒名とは異なり、「戒律を守る誓い」というよりも、「阿弥陀さまの教えに帰依した者」としての印です。亡き方が、阿弥陀如来のはたらきにより、浄土へ往生されたことをあらわすとともに、私たちに仏法を聞くご縁を示してくださる尊い名前でもあります。
初七日について

浄土真宗における「初七日(しょなのか)」とは、ご逝去から七日目にあたる日に営まれるご法要のことです。本来は、ご遺族やご縁のあった方々が故人を偲び、仏さまの教えに耳を傾ける大切な機会とされています。
浄土真宗では、故人の善し悪しを裁く「追善供養」ではなく、亡き方をご縁として、阿弥陀如来のはたらきに気づかせていただく「聞法(もんぽう)の場」としてこのご法要を大切にしています。阿弥陀さまの慈悲の中にすでに救われているという教えにふれ、故人を想いながら、今を生きる私たち自身が仏法に出遇うご縁とさせていただくものです。
現在では、葬儀当日に初七日法要をあわせて行う「繰り上げ初七日」が一般的になっていますが、日をあらためてお勤めすることもあります。どちらの場合も、形式にとらわれず、故人と向き合い、阿弥陀さまのおこころにふれるひとときを大切にしていただければと思います。